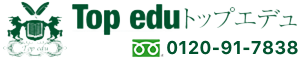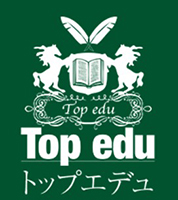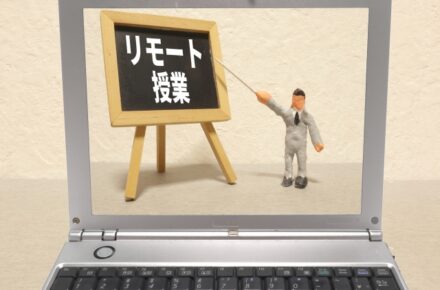「日大付属高生必見!基礎学力到達度テスト 対策と勉強法(最新版)」
基礎学力到達度テスト概要と対策・勉強方法(最新版)
日本大学附属高等学校に通う生徒の保護者様より、お問合せをいただくことが増えてきているのが基礎学力テストの対策についてです。特に保護者の方々からは、
- 「学校に任せておけばいいのか?」
- 「塾に通わせる必要があるのか?」
- 「いつからどのような対策はすればよいのか?」
という声を多くいただきます。
本記事では、基礎学力テストの特性を踏まえつつ、日大付属高生にとって有益な情報をお伝えしていきます。
基礎学力到達度テスト対策はこちらから
もくじ
1.基礎学力到達度テストとは?
2.基礎学力到達度テストの教科別対策方法
3.基礎学力テスト対策はいつからはじめればよいの?
4.塾で得られる「学力」以外の価値
基礎学力到達度テストとは?
日大付属高校から日本大学へ内部進学するためには、以下の3つの選抜方法のいずれかを通る必要があります。
- 基礎学力選抜
→「基礎学力到達度テスト」の成績で推薦を受ける方法 - 付属特別選抜
→ 定期テストや課外活動など、総合的な評価による推薦 - 国立併願方式
→ 日本大学と国公立大学を併願するための方法
このうち、「基礎学力選抜」での推薦を狙う場合、高校1年4月・2年4月・3年4月・3年9月の計4回実施される基礎学力到達度テストの結果が重要になります。
【テストのウエイトと受験科目】
| 学年・時期 | ウエイト | 共通受験科目 |
| 高1・4月 | 0% | 国語・数学・英語 |
| 高2・4月 | 20% | 国語・数学・英語 |
| 高3・4月 | 20% | 国語・数学・英語 |
| 高3・9月 | 60% | 3教科+選択科目(文理で異なる) |
高3 9月の選択科目について
- 文系:国語・数学(数Ⅲ除く)・英語+日本史/世界史/地理/倫政から1科目
- 理系:国語・数学(数Ⅲ含む)・英語+物理/化学/生物から1科目
この4回のテストの上位から希望する学部・学科に出願できますので、
高校2年生4月以降の3回のテストでしっかり得点を取ることが重要です。
【教科別の注意点】
- 国語・数学・英語は全回共通で必須科目。
- 国語では毎回、漢字語句・小説・評論・古文・漢文が出題され、古文と漢文の比重が高い(特に高3‐9月)。
- 理系志望でも古文・漢文は必須。苦手なままにせず、早めの対策が大事。
- 数学は文理で範囲と難度が異なります。文系でも数学は避けられません。
- 高3‐9月のテストには理科社会が1教科だけ入ります。この理科社会は全体の総合得点の25%を占める程の比重が高いテストになります。
【選択科目について】
- 選択科目(理科・社会)は高3‐9月の1回のみの試験です。
- たった1回の勝負のため、対策が遅れ十分な準備ができずに得点が伸び悩むケースが見られ、志望学部の合否に大きく影響します。国語・数学・英語に加えて、選択科目の早期対策も必須です。
基礎学力テストの対策方法
難易度と特徴
高3‐9月の基礎学力到達度テストは、大学入学共通テストと同レベルの難易度です。過去の定期テストとは性質が大きく異なるため、専用の対策が必要です。
特徴としては選択問題であるということが大きいです。知識の使い方、選択肢の絞り方のコツを掴むとことが肝要です。
1:苦手科目の克服がカギ!
・全科目100点満点×4科目=400点満点。
・どれか1教科で得点を落とすと、上位に入るのは難しくなります。
・得意科目を伸ばすだけでなく、苦手科目の底上げが不可欠です。
2:スピードが重要!
・どの教科も問題数が多く、時間との勝負になる。
・特に高3‐9月は範囲も広く、スピード・正確さ・判断力が求められます。
・過去問演習を通して、出題傾向と時間配分に慣れておくことが重要です。
【教科別の対策】
<国語>
・高3‐9月は古文・漢文だけで40点分あります。古文や漢文の学習は何故か軽視されがちなので、直前で焦って対策を急ぐが間に合わないケースがあります。
古文漢文は文法や句形を固めたあとは古語と古文漢文の常識を学習しよう。
・現代文は抽象度が高い文章が出題されるので、過去問だけでなく、共通テストの問題なども活用して総合的な読解力を強化。
・語句や漢字、文学史などの暗記も忘れずに。日々の積み重ねがカギです。
・文系:数学IA・Ⅱ全範囲+B(ベクトル・数列)
・理系:上記+数学Ⅲ(平面上の曲線・複素数平面・極限など)
・幅広い単元から出題されるため、苦手分野を残さないことが大事。
・応用問題も多く出るので、公式の活用や複合問題の演習にも慣れておくこと。
<英語>
・高3・9月の英語は、問題数も必要な単語数も急増する。
・長文問題の配点は100点中50点以上あり、難易度は高め。
・文法問題は点数が取りやすいので、ビンテージやネクステージで学習。
国語同様、共通テストを利用して読解力強化。高3の4月と比較すると難易度は急激に上がり、今までと同じ対策では不十分である。
外部受験が出来る程度の学力養成と対策が必要となります。
<理科・社会>
・基礎学で志望学部の合格を目指すには、早期から理科社会の対策が絶対に必要。高3‐4月の基礎学が終わるまで、全く対策をしていないと、準備期間が足りずに失敗するケースが多い。
・基礎学は高3‐9に行われる1科目の理社のテストが、全体の25%を占めるため、入念な対策をすれば上位を目指すには必須科目。思うように他の教科が取れない場合は、理社の結果次第で逆転合格も十分可能。
・どの科目も広範囲からの出題で、早期に基礎を固めておく必要がある。
基礎学力テスト対策はいつからはじめればよいの?
基礎学力到達度テストは、高校生活の中でも特に重要な試験であり、高3・9月の試験が合否に最も大きく影響します。特にこの試験でしか受けられない選択科目(理科・社会)は、たった1回の勝負であり、ここでの得点が将来の進路を左右することも少なくありません。
しかし、学校生活では日々の定期テストや課題に追われ、気がつけば基礎学テスト対策に十分な時間を確保できなかった、という声も多くあります。だからこそ、「対策はいつから始めるべきか?」という問いには、「今すぐに」と答えるべきです。
トップエデュでは、日々の学習状況を徹底的にチェック・管理しています。一人ひとりに合わせた「MYプラン」により、必要な学習の追加や計画修正を柔軟に行い、着実に成果につなげていきます。
特に高3・9月の選択科目については、定期テスト後から対策を始めても時間が足りません。トップエデュでは、高2の段階から先を見据えた学習スケジュールを立て、日頃から基礎学の過去問に触れ、自然と試験形式に慣れることができるようにしています。
やる気が出ないときは?
「努力したのに結果が出ない」「何から始めていいかわからない」そんなときもあるでしょう。トップエデュでは、そうした時期にも寄り添うために「やる気カウンセリング」を実施。小さな成功体験を共有しながら、やる気と自信を引き出すサポートをしています。
「やる気が出ないから始められない」ではなく、始めてからやる気を育てるという考え方で、私たちはあなたの第一歩を後押しします。

トップエデュの基礎学力テスト対策
トップエデュでは、基礎学力到達度テストに対して早期から計画的な準備を進めることを重視しています。
この試験は出題範囲が広く、短期間の詰め込みでは太刀打ちできません。特に高3・9月にしかない**選択科目(理科・社会)**は、たった1回の試験で配点が25%もあり、合否に大きく影響するため、早い段階からの対策がカギを握ります。
トップエデュでは、一人ひとりの学習状況に合わせて「MYプラン」を作成。定期テスト対策に追われて基礎学力テスト対策が後回しにならないよう、日常の学習の中に過去問演習や出題傾向分析を組み込むことで、基礎力と応用力を同時に育てていきます。
また、なかなか結果が出ずにやる気を失ってしまうような場面では、「やる気カウンセリング」で生徒と本音で向き合い、小さな成功体験を言語化して共有。モチベーションを高め、自信につなげるサポート体制も整えています。
短期的な結果よりも、長期的な成長にフォーカスする――それが、トップエデュの基礎学力テスト対策の強みです。
まとめ
基礎学力到達度テストは、日本大学への内部進学を目指す生徒にとって、高校生活で最も重要な試験の一つです。
特に高2・4月から評価が始まり、高3・9月には全体の60%の配点が課されるため、ここでの結果が進学の可否を大きく左右します。
英語・数学・国語の主要3科目に加えて、選択科目(理科・社会)も得点源として重要であり、苦手科目を放置せずにバランスよく対策を進めることが必要です。全教科均等配点のため、得意・不得意の差がそのまま合否に直結するケースもあります。
ただし、基礎学テストは出題傾向が大きく変わることはありません。早期からの継続的な学習と、出題傾向に即した演習を重ねることで、確実に得点力を伸ばすことができます。
トップエデュでは、こうした試験の特性を踏まえ、一人ひとりに合わせた対策を行っています。
「何を、いつまでに、どのようにやるべきか」を明確にし、あなたの努力を結果に結びつけるためのサポート体制を用意しています。
基礎学対策は、始めるタイミングで大きく差がつきます。
トップエデュで、確かな準備を早期にスタートしましょう。
基礎学力到達度テスト対策はこちらから
中高一貫定期テスト対策コースはこちら